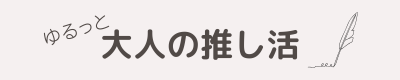推し活を楽しむ中で欠かせないのが、SNS。
ライブの感想やグッズの紹介、ちょっとした嬉しい気持ちもシェアできて便利ですよね。
でも、SNSには見えないマナーがいろいろ…。
「どこまで投稿していいの?」と不安に思うこともあるかもしれません。
迷ったときは「その言葉、親しい友人にも言える?」というのを基準にしてみてもいいかもしれません。
はじめての推し活SNSでも安心できる、やさしいマナーのヒントをぜひ参考にしてくださいね。
推し活×SNSのいいところ、気をつけたいところ

SNSは、推しの情報収集をしたり、推し友とつながれたりする楽しい場所。
でも、顔が見えないからこそ「ちょっとした言葉のニュアンス」が伝わりにくくなることも。
だからこそ、気持ちよく情報交換ができるよう「気持ちよく使えるルール」があるいいですよね。
SNSで気をつけたい8つのこと

① 公式画像や動画の無断転載はしない

「このビジュが最高すぎて…みんなに見てほしい!」
そんな気持ち、よ〜く分かります。シェアしたくなりますよね。
でもその画像や動画、もしかすると“転載NG”かもしれません。
公式が出している画像や動画には著作権があるものも多く、無断で使ってしまうと削除対象になったり、トラブルのもとに…。
「これってOKかな?」と迷ったら、
など、工夫しながら発信してみましょう♪
② ネタバレにはひとこと添える

ライブや配信の後に感想をシェアしたくなるのも、推し活の楽しみのひとつ!
でもその投稿、まだ観ていない人の楽しみをうばってしまうことがあるかもしれません。
「これからアーカイブを観るよ」という人や、「地方公演を待っている」人もたくさん。
▶︎ 投稿の最初に「ネタバレあり」と書くだけで、相手へのやさしさになりますよね。
③ 他の推しやファンを下げない
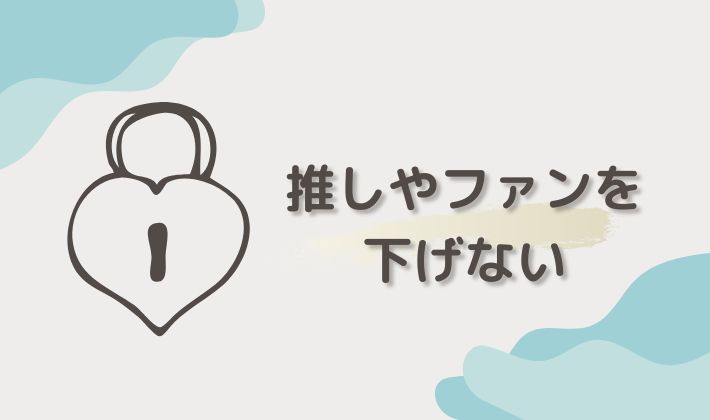
ファン同士でも、推しの形や応援スタイルはみんなそれぞれ。
▶︎ “自分の推しを褒める”ことに集中するのが、大人のSNSマナー◎
④ タグやリプの使い方に気をつける

SNSでの発信でよく使われるのが、ハッシュタグやリプライ(返信)。
推し本人が見ているかもしれないハッシュタグや、「繋がりタグ」などは、目的に応じて使い分けるのがベスト。
▶︎ハッシュタグやリプライは、使い方ひとつで「感じのよい人だな」と思ってもらえるチャンスになります。
⑤ 推し本人や関係者のプライバシーを守る

目撃情報や宿泊先、空港の利用など、リアルな動線が分かる投稿は避けるのが基本。
「偶然〇〇駅で見かけた!」「ホテルのロビーで会ったかも…!」共有したくなりますが、
推し本人や関係者のプライバシーを守るのも、ファンの大切なおしごとのひとつです。
⑥ フォロー・リムーブの挨拶文化は人それぞれ

SNSで誰かをフォローするとき、または外すときに「挨拶って必要なのかな?」「無言フォローって失礼なの?」そんな風に戸惑ったことはありませんか?
実はこの“フォローまわりのマナー”、正解があるようでない世界なんです。
それぞれのスタンスやペースがあるので、相手のプロフィールをそっと読んでから動くのが安心。
▶ リアルの距離感と同じくらい、SNSも“ちょうどいい距離感”を意識しよう
自身のSNSプロフィールにも「無言フォローOKです」など、プロフィールに書いておくとトラブル回避に◎
⑦ 自分を守る設定を忘れずに

たくさんの人が見ているからこそ、ちょっとした工夫で“自分を守る”こともとっても大切。
SNSマナー=“守るためのルール”だけじゃなく、“自分を守るため”にも使えます。
▶「推し活が楽しく続く」ために、安心できる使い方を見つけていこう
やさしさの積み重ねが、SNSをもっと心地よくする
「やりすぎかな?」「これってダメ?」と迷ったときは、
“自分がされたらどう感じるか”を少し想像してみると答えが見えてきます。
今回ご紹介したマナーやヒントは、どれも“正しく使わなきゃ”ではなく、“誰かの気持ちを大切にしたい”という思いやりから生まれたものばかり。
・SNSで自分を疲れさせないちょうどいい距離感
・誰かの楽しみを守る「ネタバレ配慮」
・推しやファンをリスペクトする言葉づかい
推し活SNSは、好きな気持ちを共有できるステキな場所。
だからこそ、“やさしい使い方”で、もっと心地よい空間にしていきましょう✨